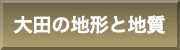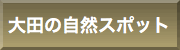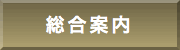■石見銀山と自然との共生を考えるコラム
石見銀山の「自然との共生」とは?
石見銀山は環境に配慮しながら開発した鉱山だったから世界遺産になったと言われることがあります。2007年7月の世界遺産の時、事前に国際記念物遺跡会議(ICOMOS)が出した登録延期勧告をくつがえす切り札となったのが、自然と共生した開発という補足説明だったと言われます。以来、この言葉は石見銀山を紹介する際にしばしば使われるようになりました。
石見銀山は自然と共生した鉱山だったのでしょうか。
そもそも自然との共生とは何を意味しているかと考えると、言葉だけが一人歩きして本質が曖昧なままになっているように感じます。石見銀山に限らず、自然との共生という言葉の捉え方は人によってまちまちで幅広い解釈が可能なだけに違和感を感じることは少なく、言葉が一人歩きしてしまっていることに気づくことはないかも知れませんが、自分自身が理解できていない言葉を使ってしまうことは避けたいと思います。
あらためて、自然との共生とはどういうことでしょうか。石見銀山の開発が自然と共生していたかということと、石見銀山の中心的な価値は自然との共生なのかという2点に分けて整理してみたいと思います。
石見銀山の開発が自然と共生したものであったかということは、どこに視点を置くかによって見え方が変わるかも知れません。鉱山開発は大地をうがち、燃料を燃やして資源を得る行為です。人類による自然破壊をともなう行為の切っ先であり、その観点で見ると自然と共生した鉱山開発は「あり得ない」と言うことになります。「鉱山という自然に対する破壊行為でありながら、石見銀山の場合は・・・」という前提の上で、自然との共生という言葉をとらえる必要があると思います。
では、石見銀山の開発では自然に対する特別な配慮が行われていたのでしょうか。
江戸時代には幕府(代官所)が管理する重要な鉱山だった石見銀山は、中小の鉱山に比べると開発や人員の管理が合理的、人道的に行われていた印象を受けます。許可制によって開発範囲や規模が定められたり、社会福祉を考えた雇用形態であったことなどが記録からうかがい知ることができます。そのためか、開発の跡地も整然としており、残土の山が放置されているような場面はほとんどありません。しかし、このことが自然との共生に当てはまるとは言い難いでしょう。
石見銀山では緑を回復するために植林が行われていたから自然と共生していたと言われることもあります。植林しながら開発したから、現在の緑に覆われた景観があるという表現を見聞きすることもあります。植林が行われたことは記録されており、そのことを切り取って自然と共生した開発と言うこともできなくはないかも知れませんが、植林は木材や薪、炭の確保の目的や治水や地盤の強化を目的にごく普通に行われてきたことです。植林を石見銀山の特別性と言うことは少々無理があります。
現在の石見銀山遺跡地内が緑に覆われていることは、日本列島では当たり前の光景です。気温と降水量に恵まれた日本列島では、開発によって裸地化した土地も数十年で樹木に覆われ、100年も経てば森林になります。鉱山では強い酸性成分や硬質な岩盤がむき出しになることによって植生の回復が遅れることはあるものの、国内の廃鉱山のほとんどは緑に覆われています。このことも自然との共生という言葉を当てはめることには躊躇する事実です。
ここまでの整理は、石見銀山では自然に配慮した開発を行い、自然と共生していたということを否定する内容でした。鉱山開発の表面的な行為では、石見銀山で特別な自然への配慮を行なっていた事実はないと思うのですが、自然との共生という言葉を否定するつもりはありません。世界的な視点で見ると、石見銀山の開発は自然に対する一定の配慮があり、それを共生ということができると思います。ただし、石見銀山が特別なのではなく、日本の鉱山開発が世界の多くの事例と比較した時に特別なものだったということで、そのことが注目されるきっかけが石見銀山遺跡の世界遺産登録だったと思うのです。
古来、自然崇拝的な信仰感を持っていた日本の人々は、岩や山など大地に神が宿ると考え、鉱山開発でも山の神をまつって祈りを捧げてきました。そのような信仰感を持つ人々が自然に対して乱暴な開発を行わなかったことは想像に難くありません。
薪や炭といった燃料資源の確保は、植林を行うなどによって新しい木を育てながら行う循環型の開発でなければすぐに足りなくなってしまいます。鉱山開発に携わった人々は鉱山地内で暮らしており、強引な開発は自分たちの住環境に悪影響を及ぼすことになります。その経営単位は小さく、経営者と雇用者の関係は近く、雇用者を大切にすることが経営の安定にもつながりました。これらが日本の鉱山の開発であり、ヨーロッパの人々にとっては異質なものに見えたのです。
日本列島に比べて緯度が高く冷涼な気候の範囲が広いヨーロッパでは、森林伐採は長期間にわたる森林消失の原因になります。鉱山開発で裸地化した土地は長期間に渡って裸地の状態が続く可能性が高いです。
鉱山労働者には奴隷が使われたり、南米あたりでは現地住民を奴隷に近い形で使うことが行われました。管理者、経営者は鉱山地内に住まず、時には人道を無視した開発が行われることもありえたでしょう。このような開発が行われた鉱山は植生が回復していない場合もあり、採掘の後には雑然としていることもあり得ます。これがヨーロッパの人々が知っている鉱山なのです。
大地を大切にしながら開発を行なってきた日本の鉱山は、ヨーロッパの人々が携わった鉱山の開発様式とは大きく異なる場合があり、両者を比較すると日本的な鉱山開発は自然と共生していたと言えるでしょう。石見銀山を視察したICOMOSの人々が「自然との共生」を感じたのはそのためで、否定されるものではないと思われます。同時に江戸時代までの日本的な循環型社会は、自然との共生なしに成立しないものと言うことができ、石見銀山でその一断面を知ることには大切な意義があると思います。
なお、自然との共生していたことの要素として、石見銀山では目立った鉱害がなかったことに触れられる場合もありますが、これは鉱物組成の幸運と、鉄や銅に比べると生産規模がずっと小さいために煤煙による鉱害が目立ったなかったという事情によるもので、環境への配慮の結果とは言えないでしょう。
次に自然との共生が石見銀山の中心的な価値なのかということについてですが、石見銀山の開発で自然に対する特別な配慮が行われたわけではないとすれば、これを価値の中心に位置づけることは難しいでしょう。
石見銀山の中心的な価値は、16世紀から17世紀初頭にかけて当時としては大量の銀を産出して国内外の政治経済や文化交流に影響を及ぼしたことと、それを示す全体像が遺跡としてよく残り、地域の社会景観や文化の中にもその面影をとどめているということが第一でしょう。このことを抜きにして石見銀山の価値は説明できないのです。
自然との共生という言葉は、ICOMOSの調査団が発した感想がきっかけとなり、世界遺産登録に向けた捕捉的な説明として加えられたものでした。この言葉が当落線上から落ちかかっていた石見銀山遺跡を世界遺産登録へ押し戻したことは確かです。しかし、改めてこの言葉を使う時には、それが何を意味しているのかを意識しておきたいと思います。
中村唯史(放送大学講座用原稿)
石見銀山に学ぶ
「自然との共生」。
これは石見銀山の世界遺産登録の際のキーワードでした。地球環境の将来への関心が高まる今日、この言葉は強い説得力を以て受入れられ、その後折りに触れて耳にします。石見銀山における自然との共生とは何か。改めて考えると、思いがけず説明に窮します。心地よい響きの一方で、真意が判り難い言葉です。自然との共生と対極にあたる鉱山開発。矛盾をはらんだ言葉には石見銀山の時代の人と自然の関わりが込められているように思います。
銀山の本体、仙ノ山の山中を歩くとある錯覚を憶えます。何百年にもわたって岩を砕き火を燃やし続けた荒廃の色は希薄で、むしろ整然とした遺構と各所に残る石塔に信仰の山の静寂を感じるのです。世界の鉱山を知る海外の研究者が調査に訪れた際、この光景に驚きを感じたのも無理ありません。ヨーロッパや南米の鉱山跡は植生が失われ、人工物が支配する空間であることが多いと聞きます。中世の大銀鉱山でありながら静けさが漂う石見銀山は、世界的には異質な存在なのです。そこに「自然との共生」に通じるものがありそうです。
石見銀山遺跡の大部分は森林に覆われています。緑は自然豊かな印象を演出してくれます。森林は「自然との共生」の鍵です。しかし、緑が豊かなのは環境に配慮した開発の結果というわけではないでしょう。近世以前は、鉱山開発に限らず燃料の大半を森林に依存していました。その需要は膨大で、森林は限界近くまで利用されたのです。石見銀山も例外ではありません。それでも日本の森林は強靱です。恵まれた気候のおかげで、裸地化しても数十年で木が生え揃います。使っても再生する森。恵まれた気候条件と島国という地理的条件は、日本的な自然観を育みました。近世以前の日本人にとって、自然は感謝と畏れの対象でした。自然は恵みをもたらしますが、狭い国土では己の土地がもたらす実りが唯一の生活の糧でもあります。環境に大きな打撃を与えると暮らしが成り立たなくなります。感謝と畏れの念は、生きるために自然を利用し、生きるために自然と折り合いをつけることから生まれた自然観なのです。それは民族の移動と争奪を繰り返した大陸的な自然観とは異質です。また、どこか第三者的な感がある現代の自然保護の概念とも異なります。限られた土地の自然を利用した日本の生活は、自然を支配するものでも隔離するものでもなく、共生していたと言えるでしょう。
近世以前の鉱山開発も日本的自然観に基づいて行われました。山に神を祀ったことはその表れのひとつです。鉱山の周辺には人々の暮らしがあり、それは奴隷制や植民地支配のもとで開発された欧米の鉱山とは異なるたおやかなものでした。石見銀山に漂う静謐は、そのような開発と生活の痕跡が時の流れとともに風化する過程で生まれたものであり、故に景観の中に自然と共生した精神が感じられるのだと思います。それは当時の日本の精神性であり、石見銀山だけが何か特別な意識に基づいて開発されたのではないでしょう。しかし、国内外に多大な影響を及ぼした銀山に自然との共生の意識に基づく開発の痕跡が遺存することは他に比類なく、日本的自然観の象徴として世界に誇り得るものに違いありません。
ところで、世界遺産登録の際に自然との共生がキーワードとなった背景には、世界的な将来環境への関心の高まりがあったと聞きます。鉱山でありながら環境負荷が小さかったことが注目されたのです。人類はいつの時代も自然から資源を得て生活しています。石見銀山の時代は森林が再生する早さと量の範囲での生活でした。現代はそれでは間に合わず、化石燃料をはじめ膨大な量の地下資源を用いています。地球には様々なスケールの物質循環があります。その速度と量を超えて資源を利用すると、枯渇と環境負荷が生じます。自然の循環は環境を考える上で重要な要素です。現代人は自然に生かされていることを忘れかけていますが、図らずも限られた土地で生活してきたいにしえの日本人は自然の循環を強く意識し、上手に利用してきました。石見銀山遺跡の静謐。それは現在と未来の社会にとって大切なことを教えてくれると感じます。
中村唯史(石見銀山一心会会報用原稿)