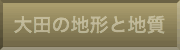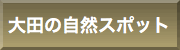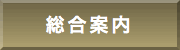■三瓶山の火山史と三瓶小豆原埋没林
1.火山噴火で生まれた山
1)三瓶山の概要
三瓶山は島根県の中央部に位置する。日本海の海岸からは直線距離で約15kmと近い距離にあり、山陰山陽の境をなす中国山地脊梁からは北に離れた独立峰である。
三瓶山は火山であり、中国山地の隆起とは直接的な関係がなく、火山噴火によって山体が形成されたことが、その立地と関わり深い。
三瓶山の峰は主峰の男三瓶山(1126m)をはじめ、子三瓶山(961m)、女三瓶山(953m)、孫三瓶山(903m)、太平山(854m)が室ノ内と呼ばれるくぼ地を囲んで環状に配列している。環状列の南には日影山(697m)と無名のピーク(718m)が並び、男三瓶山の北には天上原の名称があるテラス状の小ピークが張り出している。テラス状の地形は、男三瓶山の西にもあり、机ケ背の名称がある。男三瓶山、子三瓶山、女三瓶山、孫三瓶山、日影山および無名のピークは、デイサイト溶岩(*1)からなる溶岩円頂丘である。太平山は火砕物が堆積して形成された火山砕屑丘(*2)とされている。
峰々の外側は、帽子のつば状に緩斜面が取り囲み、西の原、東の原、北の原(長者ケ原など)と呼ばれる。緩斜面の外側は標高400〜500mのピークが連なる低山帯で、火山としての三瓶山の基盤にあたる岩石(*3)が分類している。すなわち、三瓶山の火山地形は緩斜面部分までで、その範囲は直径約5kmの円形である。この部分は古期の火山活動で形成されたカルデラ(*4)で、現山体はカルデラ内に形成された中央火口丘群という言い方もできる。
三瓶山は過去約10万年間に複数回の活動を行った火山で、最新の活動は約4000年前である。気象庁による区分(*5)で活火山に指定されている。

図1-1 三瓶山の地形(地理院地図を使用)
*1 デイサイト:火山岩の一種。4)三瓶火山の噴出物と火山岩について で詳しく述べる。
*2 火山砕屑丘:火口付近に軽石、火山礫、火山灰が堆積してできた高まり。
*3 基盤にあたる岩石:三瓶火山噴出物の下には、古第三紀の花崗岩類、新第三紀の火山岩類が分布している。
*4 カルデラ:直径2kmを超える噴火口をカルデラと呼ぶ。室ノ内は直径2km未満のため、カルデラとは呼ばない。
*5 気象庁による区分:概ね1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」を活火山と定義されている。現在、全国で110ヶ所。
2)火山の基礎
マグマ(*1)が溶岩として地表に噴出したり、火砕物(*2)が噴出してできた地形を火山と呼ぶ。火山活動時には溶岩と火砕物だけでなく、マグマに由来する水蒸気や硫化水素、二酸化炭素などのガス成分も噴出される。
マグマは、地下深部で岩石、特にマントルを構成するカンラン岩が融解して生成されると考えられている。マグマが生成される場所は、中央海嶺のマントル湧昇部と、プレートの沈み込み帯、ホットスポット(*3)に大別される。
日本列島はプレートの縁辺部にあり、日本列島の火山は基本的に海洋プレートの沈み込みに関係している。日本列島の地下深部には海洋プレートが沈み込んでいる。これが地下100km以深の深さまで沈むとその温度は千数百度に達する。この時、プレートは個体の岩石だが、岩石中の水がマントル中に放出されると部分的な溶解が生じマグマが生成される。この時の温度は1300℃以上とされる。
日本列島の火山の多くは列状の分布(*4)を示す。プレートの沈み込みによりマグマが生成される深度の等深線がこの列に一致する。本州、九州、北海道の火山分布を見ると、火山列を境に大陸側には火山が存在するが、太平洋側には火山が存在しない。太平洋側は沈み込んだプレートが、マグマが生成される深度まで達していないため、火山が形成されない。このように、火山が出現する境界線は火山フロント(前線)と呼ばれる。

図1-2 活火山の分布と火山フロント

図1-3 日本列島周辺のプレートの動きとマグマ生成のイメージ
*1 マグマ:地下にある、岩石が溶融してできた液体。岩石成分と水などの揮発性成分が混合した液体。地表に噴出したものは溶岩と呼ばれる。
*2 火砕物:固結したマグマが砕けた土砂状の物質。火山礫や軽石、火山灰。
*3 マントルの対流と関係なく、定点で火山活動を生じる場所。ハワイ火山がこれにあたる。
*4 列状の分布:以前は「火山帯」と表現したが、現在はほとんど使われなくなっている。
3)火山噴火のメカニズム
地下深部で生成されたマグマが地表まで上昇し、噴出する現象が火山噴火である。休止期を挟んで間欠的に噴火する火山が多いが、1度だけ噴火して活動を終える火山もある。桜島火山(*1)や阿蘇火山のように頻繁に噴火を繰り返す火山もある。
マグマが上昇し噴出する主な原動力は、気体成分の泡立ちによる膨張、圧力上昇と考えられている。地下深部でマグマが溜まってくると、周囲の岩石よりも軽いために浮力が働き上昇しようとする力が生まれる。
マグマ中には水蒸気や二酸化炭素、硫化水素などの気体成分が多量に含まれていて、地下深部の高温高圧条件ではそれらはマグマ中に溶けている。しかし、マグマが上昇を始めて、外圧と温度が低下すると溶け込んでいられなくなった気体成分が泡立ち、マグマが膨張する。膨張することで内圧が高まるとともに、周囲の岩石との密度差が大きくなり(=相対的に軽くなり)、上昇しようとする力が強まり、上昇速度が加速される。
マグマが上昇する経路は、断層による割れ目など、岩盤の弱い部分である。上昇速度が速くなると、泡立ちが加速度的に生じてさらに加速させる。一方、上昇速度が遅いと泡立ちが少なく、気体がゆっくり放出されることで内圧が低下し、マグマが地表に達することなく停止することもある。
地表直下に達したマグマが沸騰するように激しく泡立つと、爆発的な噴火によって一気に放出され、大噴火を引き起こす。地下のマグマの圧力によって火口から溶岩が押し出されるように出てくる噴火、マグマ本体は火口深部にあり、水蒸気などの気体だけを放出する場合、マグマと地表付近の水が接触することで生じる水蒸気爆発(*2)など、噴火の形態は様々である。

図1-4 マグマの泡立ちによる火山噴火のイメージ
*1 桜島火山:鹿児島県の錦江湾を作る姶良カルデラの中にある火山(中央火口丘)。極めて活発に噴火を繰り返す、世界でも有数の活動的な火山。
*2 水蒸気爆発:地下水や地表水がマグマと接触し、急激に気化することで生じる爆発。
4)三瓶火山の噴出物と火山岩について
マグマが地表に噴出したものは溶岩と呼ばれ、溶岩が固結してできた岩石は火山岩と呼ばれる。ただし、固結した岩石についても、成因で分類する場合は固結した溶岩をそのまま溶岩と呼び、成分で分類する場合は火山岩の名称で呼ぶ場合がある。つまり、同じ岩石を表現の意図によって溶岩と呼んだり、岩石名で呼んだりすることがある。
火山岩の区分は、その主要成分のひとつ、二酸化ケイ素(SiO2)(*1)の多少によって区分される。二酸化ケイ素が多い方から、流紋岩、デイサイト、安山岩、玄武岩、超塩基性岩に区分され、例えばその量が63%より多ければデイサイト、少なければ安山岩といったように、成分の多少によって機械的に分けられる。
SiO2の多少は、粘性が高い、低い、といったマグマや溶岩の性質に関係が深く、その多少によって溶岩の流動性や、噴火の様式に直接的に関係する。SiO2が多いマグマは粘り気が強く流れにくい。少ないマグマは粘り気が小さく流れやすい。具体的には、ハワイのキラウエア火山の溶岩は粘り気が小さいため、溶岩流が川のように流れるが、三瓶山の溶岩はSiO2が多く、溶岩は余り流れず火口付近に小高い溶岩ドーム(*2)を形成する。
三瓶火山の噴出物は、第1活動期は流紋岩質、第2活動期以後はデイサイト質である。現山体は、デイサイト溶岩と火砕物からなる溶岩円頂丘(鐘状火山、トロイデ火山)の集まりで構成されている。三瓶火山のデイサイトは、鉱物として斜長石、黒雲母、角閃石、磁鉄鉱を多く含む。鉱物の粒子間を埋める「石基」(*3)と呼ばれる部分は、灰〜赤灰色を示す。色味の違いは、含まれる鉄分の酸化状態によるもので、温度が高い溶岩が地表近くで酸素に触れると「高温酸化」と呼ばれる現象によって赤みを帯びるようになる。

図1-5 火山岩の区分と火山地形
*1 二酸化ケイ素:岩石の最も主要な成分で、地殻を作る物質のおよそ60%が二酸化ケイ素。様々な鉱物に含まれる。石英(水晶)や玉髄(メノウ、碧玉)は二酸化ケイ素からなる鉱物。
*2 溶岩ドーム:粘性が高い溶岩によってできる小高い山体。溶岩円頂丘と溶岩ドームは同義だが、ここでは便宜的に火口付近にできる小規模なものを溶岩ドーム、その積み重ねによって大規模に発達したものを溶岩円頂丘と呼び分ける。
*3 石基:火山岩は多くの場合、火山ガラスや微小な鉱物結晶からなる部分と、肉眼で識別可能な大きさの鉱物結晶からなる。前者を石基、後者の鉱物結晶を斑晶と呼ぶ。火山ガラスとは、マグマが急冷されることで、結晶化が進む前に固結したもの。
2.三瓶山の噴火がもたらしたこと
1)大噴火とカルデラの形成
三瓶火山は約10万年前に活動を始め、約4000年前までに7回の活動を行ったことが明らかになっている。古い時期の活動では多量の軽石と火山灰を放出する大規模な軽石噴火(*1)を行った。第1活動期に噴出された「三瓶木次軽石」は、三瓶山から北東方向に広く分布しており、遠方では東北地方でも分布が確認されていて、日本の代表的な広域テフラ(*2)のひとつに数えられている。松江市付近では、段丘上などに50cm以上の厚さで堆積している。中海の大根島では大根島玄武岩(*3)の上に三瓶木次軽石と大山松江軽石が厚く堆積していて、この軽石土壌がボタンと薬用人参の栽培土になっている。
約5万年前の第2活動期では大規模な火砕流「大田軽石流」を発生させた。火砕流は火砕物と火山ガスが一体となって流れる現象である。その堆積物は大田市の平野部で残丘として分布しており、その層厚は20mを超える。5万年前頃は氷期中で、海面高度が低かったため、当時の海岸線は現在より沖側にあったと推定される。大田軽石流は海まで達したと考えられる。大田軽石流を発生させた大噴火によって三瓶山には直径約5kmに達するカルデラが形成された。
第4活動期までは軽石噴火を行い、溶岩の噴出は少なかったとみられる。大きな火山体は形成されず、火山活動後はカルデラのくぼ地と中央火口丘として火山砕屑丘が残る程度だったと思われる。カルデラ湖が形成された時期もあったかも知れない。
カルデラ地形は第4活動期以降の噴出物で埋もれ、カルデラ壁は明瞭ではないが、地形的にはカルデラの範囲を容易に識別できる。カルデラの内側は三瓶火山の噴出物が分布していて、溶岩円頂丘のすそ部は起伏の小さななだらかな地形である。カルデラの外側は古第三系(*4)〜新第三系(*5)が分布していて、浸食谷が発達した丘陵地である。

図2-1 三瓶火山の活動期と年代

図2-2 三瓶木次軽石(降下火山灰)の分布範囲と地層の厚さ
*1 軽石噴火:プリニー式噴火。マグマの急激な発泡により軽石など多量の火砕物を放出する爆発的な噴火。噴煙を1万m以上の上空まで噴出し、地球規模で気候に変化を与える場合もある。
*2 広域テフラ:空中に放出された軽石や火山灰を総称してテフラと呼び、広い範囲に分布して地層の年代を知る指標となるものは広域テフラと呼ばれる。代表的なものに、約2.7万年前の姶良Tn火山灰(AT)、約7300年前の鬼界アカホヤ火山灰(K-Ah)がある。
*3 大根島玄武岩:大根島は約20万年前に活動した火山で、玄武岩溶岩の噴出によって形成された溶岩台地。噴火は陸上で起きたが、海面上昇によって島になった。
*4 古第三系:約6500万年前から約2500万年前までを地質時代で古第三紀と呼び、その時代に形成された地層、岩体を総称して古第三系と呼ぶ。
*5 新第三系:約2500万年前から約340万年前までを地質時代で古第三紀と呼び、その時代に形成された地層、岩体を総称して新第三系と呼ぶ。
2)現在の山体ができるまで
三瓶山の峰はデイサイト溶岩からなる溶岩円頂丘で、太平山だけは火砕物が堆積してできた火山砕屑丘とされている。山体の中で最も古い部分は南側に位置する日影山一帯(*1)とされ、約1万9000年前の第4活動期に噴出された溶岩である。第4活動期には、大規模な軽石噴火(三瓶浮布軽石)と溶岩の噴出を行った。
日影山以外の山体は、大部分が第6活動期(約5500年前)、第7活動期(約4000年前)の噴出物で構成されている。なお、約1万1000年前の第5活動期の噴出物は、火口から数kmの範囲に少量の火山灰をもたらしている程度で、大規模な溶岩噴出はなかったとみられる。
第6活動期、第7活動期は、比較的ゆっくりとした溶岩噴出により溶岩ドームを形成し、時折、数千mの高度まで噴煙を上げる爆発的な噴火を行った。この時期の噴出物は発泡度が高い軽石(*2)をほとんど含まず、結晶化が進んだ岩片が主体で、マグマの上昇速度は遅かったと推定される。溶岩噴出で形成される溶岩ドームは、爆発的な噴火や形状の不安定化により一部が崩壊することがある。1990年〜1995年の雲仙普賢岳の活動では、火砕流の発生回数は6000回を超えた。三瓶山の第6活動期、第7活動期は、その規模(*3)に勝るとも劣らないものだったと推定される。崩壊を繰り返しながら溶岩ドームが成長し、男三瓶山、女三瓶山、子三瓶山、孫三瓶山が形成された。
三瓶山のそれぞれの峰は個別に成長したと推定されるが、以前は大きな山体が爆発的噴火によって壊れた残骸が個々の峰という見方もあった。各峰の形状は均整がとれていて、個々に形成された溶岩円頂丘と見るのが妥当である。各峰が環状の配列に形成された後、中心部の低地で最末期の爆発的噴火が生じ、太平山など火口縁の地形が形成されたのであろう。
男三瓶山の山頂には、第7活動期の噴出物の上に、クロボク層を挟んで厚さ50cm程度の火山灰層が重なる。クロボク層からは2000年前前後の放射性炭素年代が得られていて、弥生時代以降に三瓶火山が小規模な噴火を行った可能性を示唆する。しかし、他地点では同様の火山灰層は確認されず、この時期に火山活動があったことは確実ではない。

図2-3 三瓶山の地質図

図2-4 火砕流発生のイメージ
*1 日影山一帯:日影山とその東のピークは、第4活動期の噴出物である「三瓶浮布軽石」に含まれる溶岩片と同質の溶岩でできている。
*2 発泡度が高い軽石:高温のマグマが急激に上昇して激しく泡立つと軽石が形成される。この時、マグマの大部分は火山ガラスとなって固結する。マグマが徐々に冷却されると結晶化が進む。
*3 (雲仙普賢岳の活動)規模:雲仙の平成噴火の噴出物は、約2億m3と見積もられている。三瓶山の場合、男三瓶山単体でも約5億m3あり、男三瓶山の形成だけで平成噴火の規模を上回る。
3)平野形成に与えた影響
三瓶火山の活動は、三瓶山を流域とする河川の河口部に発達する海岸沖積平野(以下、沖積平野)の地形形成に影響を及ぼした。
沖積平野とは、概ね過去1万年間(*1)に河川が運搬した土砂が河口付近に堆積して形成された三角州と扇状地からなる地形である。三瓶火山の影響を受けた沖積平野には、出雲平野、大田平野、江津平野があり、特に出雲平野の地形発達に大きな影響を及ぼした。
出雲平野は島根半島と中国山地北縁に挟まれた低地帯(*2)に発達する沖積平野で、山陰地方で最大規模の平野である。主に斐伊川と神戸川の堆積物からなり、平野西部の神戸川三角州、扇状地地帯の現地形の原形は、三瓶火山の噴出物によって構成されている。
三瓶火山の第6活動期、第7活動期の際、山麓に多量の噴出物がもたらされ、その一部は神戸川の洪水を引き起こしながら下流まで運ばれた。海岸部まで泥流が達したこともあった。その洪水堆積物、泥流堆積物は神戸川扇状地にあたる範囲で、3〜5mの層厚で分布しており、その規模の大きさがうかがわれる。出雲平野西部にはこの堆積物が広く分布していて、その堆積年代が第6活動期、第7活動期に一致することが明らかになっている。出雲平野西部では、微高地に弥生時代の遺跡が集中し、そのような場所は近現代まで集落の中心として利用され続けてきた。微高地の地盤は第7活動期の噴出物でできており、現地形の基本となる地形が、火山活動期の大規模な洪水によって形成されたことを物語る。
静間川、三瓶川(静間川水系)の下流に発達する静間川下流低地と三瓶川下流低地もその大部分が三瓶火山の噴出物で構成されている。この水系への火砕物の供給量は神戸川以上だったと推定されるが、静間川河口が日本海に直面しているために平野拡大の余地が少なく、出雲平野に比べると地形発達への見かけの影響は小さい。江の川の場合も同様で、河川規模に対して下流部の平野が著しく貧弱であるため火山活動の影響は、見かけ上は小さく見える。

図2-5 出雲平野西部の南北方向断面図(断面位置は図2-6参照)

図2-6 出雲平野西部の微地形と遺跡立地

図2-7 中海・宍道湖周辺地域の過去1万年間の古地理変化
*1 概ね過去1万年間:最終氷期が終わり、現代までの温暖期を地質時代の区分で完新世と呼ぶ。完新世の始まりは約1万1000年前とされる。完新世初頭には海面は現在より30〜40m低く、7000年前にかけて急上昇して現海面程度の高さになった。海岸沖積平野は現海面高度に対応してできた地形面なので、その堆積物は概ね1万年前以降のものが中心である。
*2 低地帯:出雲平野、宍道湖、松江低地、中海、弓ヶ浜半島と連なる沖積平野、潟湖が発達する低地帯を「宍道低地帯」と呼ぶ。
4)三瓶山の噴火と考古遺跡
三瓶火山の活動は日本列島で人類が活動を始めた頃に始まり、縄文時代にも3回の活動を行っており、その噴出物に覆われた遺跡、火山灰層が見いだされた遺跡が幾つも存在する。
旧石器時代では、奥出雲町の原田遺跡(*1)で第4活動期(約1万9000年前)と第3活動期(約4.6万年前)の噴出物に挟まれた古土壌から複数時期の石器が多数出土した。ここでは姶良Tn火山灰(2万7000年前)も確認され、その下からも石器が出土している。広島県庄原市の帝釈峡遺跡でも、第4活動期の噴出物の下から旧石器が出土している。第4活動期の噴出物は、三瓶山以東の中国山地において、旧石器遺跡を探す指標(*2)となる存在である。
縄文時代では、飯南町志津見の板屋III遺跡で第7活動期、第6活動期、第5活動期の噴出物の下からそれぞれ多数の遺物が出土している。ここでは縄文時代後期の土器にイネの籾痕が付いていたものがあり、その時代にすでにイネの栽培が行われていたことがうかがわれる。
出雲市の三田谷I遺跡(*3)や築山遺跡では、第7活動期の噴出物に由来する洪水堆積物の下から縄文時代の遺物が出土している。この活動期には、出雲平野は火山噴出物由来の洪水堆積物に広く覆われており、これに覆われた未知の遺跡がまだまだ存在すると推定される。
縄文時代の遺跡で三瓶火山の噴出物が確認された例は多く、日南町の霞遺跡でも第6活動期の噴出物が確認されている。
鬼界アカホヤ火山灰をもたらした約7300年前の鬼界カルデラの巨大噴火では、南九州の縄文文化が一時断絶したとされる。その噴火に比べると三瓶火山の活動は規模が小さく、広い範囲が居住不能となるほどの影響はなかったと考えられる。しかし、神戸川などの下流域は火山活動時には洪水が繰り返され、河岸での居住は不可能だったと推定される。魚などの生物資源の回復にも、火山活動終了から数10年程度は要したと思われる。
*1 原田遺跡:斐伊川中流域の河岸段丘に立地する遺跡。後期旧石器から中世に至る遺跡。尾原ダムの建設に伴って発掘調査された。
*2 旧石器遺跡を探す指標:火山灰で地表が厚く覆われることで、遺跡が保存されやすくなるため、火山灰層の下からは遺物、遺構が発見される確率が高い。
*3 三田谷I遺跡:神戸川扇状地の扇頂部に近い枝谷が火山噴出物に由来する洪水堆積物で埋まった場所に立地する遺跡。洪水堆積層の下からも縄文の遺物が出土した。
3.三瓶小豆原埋没林と原始の森
1)原始の森の意義
三瓶小豆原埋没林は、約4000年前の森が、火山噴火によって地中に埋もれたもので、いわば森林の化石である。樹木が原位置のままに立ち、古土壌(*1)には林床の落ち葉や種子、昆虫化石(*2)までも原位置に残り、原始の森の環境がほぼそのまま保存されている。現在の日本列島の森林は、その大半が人の手が加わった二次林(*3)や人工林で、自然状態の森は極めて少ない。人の手が加わらない条件での植生である。三瓶小豆原埋没林は、過去の森林環境を現代に伝える資料として極めて貴重な存在である。埋没樹木は直径1mを超える大径木が多く、残存する幹高が12mを超えるものもある。幹まで残る埋没林は極めて珍しく、その大きさも世界的に例が少ない。
過去の生態系や環境を知ることは、現在を理解し、将来の変化を予測するために欠かせない作業である。過去の生物の情報は化石から得ることができる。化石の中で、生息環境でそのまま埋もれたものは「現地性化石」と呼ばれ、古環境を推定したり、その生物の生態を知る上で重要な資料となる。化石には水流などに運搬されて地層中に取り込まれたものが多く、現地性化石は貴重である。とりわけ、埋没林のようにその場の生態系がそのまま化石になったものは重要度が高い。
三瓶小豆原埋没林は、縄文時代の三瓶山北麓にスギを中心とする林が存在したことを証明した。現在、中国山地に自生のスギ林はほとんど存在せず、高所に断片的に自生のものがみられるにすぎない。約4000年前と現在は、気候的にはそれほど大きな違いはなく、植生の違いを生んだのは主に人の手による開発の影響である。特に、近世に製鉄(*4)が盛んに行われた中国山地は山林開発が進み、原始的な植生はほとんど残存していない。その失われた植生を示すのが三瓶小豆原埋没林であり、現在も自然状態で長時間かけて森林が形成されると、類似の環境にはスギ林が成立する可能性が高い。

図3-1 三瓶小豆原埋没林の出土樹種構成(立木・流木)
*1 古土壌:地層中に埋もれた過去の土壌を古土壌と呼ぶ。三瓶小豆原埋没林では古土壌が完全な形で残っている。
*2 昆虫化石:三瓶小豆原埋没林の古土壌からは多数の昆虫化石が出土する。オオスジコガネなど、針葉樹林に多い甲虫のほか、糞虫の仲間が多い。落ち葉の下に集まったアリがそのまま出土した例もある。
*3 二次林:人為的な伐採の後に形成された森林。
*4 製鉄:近世の中国山地は全国一の製鉄地帯だった。たたら製鉄では多量の炭を使うため、中国山地の森林の大部分は薪炭林として利用された。
2)原始の森の姿
三瓶小豆原埋没林の出土樹木は、スギが過半数を占め、特に大径木では圧倒的にスギの割合が高い。当時、埋没林付近の谷筋には、スギを主体とする極相林が分布していたことを示している。出土したスギは直径1mを超える大径木が多く、立木は出土状況から平均10m前後の間隔で立ち並んでいたとみられる。大きなものでは胸高付近の直径が2mを優に超え、現生の同等の太さのスギから推定すると、埋没林のスギの多くは樹高40〜50m(*1)に達していたとみられる。これほどの巨木が比較的近い間隔で生育することから、林内はかなり暗い環境だったはずである。このような森林では、他の樹木が侵入することが難しいため、比較的暗い場所で生育できる「陰樹」が圧倒的に優先し、変化が小さい状態が続く。この状態の森林が極相林である。
三瓶小豆原埋没林で年輪が計数できた立木は3本ある。いずれもスギで、年輪数が多いものから636本、443本、約400本の順で、この森の形成には少なくとも600年以上かかっている。埋没林の古土壌の花粉分析によると、タンポポなどの草本類が生える草地から、スギ林に変化した過程が推定されている。
流木も含めた樹種鑑定151点の結果では、スギに次いで多いのはカシ類とトチノキである。島根県内で行われた地層の花粉分析からは、縄文時代前期以降は、海岸に近い丘陵地帯はカシやシイを主体とする照葉樹林(*2)が広がり、谷筋にはスギが多かったと推定されている。三瓶小豆原埋没林の出土樹種はその傾向に近い。ただし、流木は土石流に運ばれたもので、谷筋に生えていたものが中心となるため、ここで判明した樹種構成は、基本的には谷筋の植生(*3)を反映していると考えられる。
埋没林の古土壌には、サルナシやキイチゴなどの低木の種子が多数含まれている。枝や葉は見つかっておらず、種子は動物の糞に含まれるなどして運搬されたものと推定される。コケの葉は多数みつかるため、林内は暗く、低木や草本類が繁茂することはほとんどできない環境だったと考えられる。

図3-2 発掘調査で確認された埋没樹(立木)の位置
*2 照葉樹林:カシ、シイ、タブノキなど常緑の広葉樹からなる森林。社寺林にみられることがある。
*3 谷筋の植生:スギは谷筋の湿度が高い環境を好む樹種で、カシやシイなどはそれに比べると乾燥した環境を好む。
3)埋没林の発見
三瓶小豆原埋没林の発見は、高校教員だった松井整司氏の功績によるところが大きい。松井氏は大田高校勤務時代に三瓶火山の研究を始め、主要な火山灰の分布と火山活動史を解明した。埋没林との関わりは1990年頃に、小豆原地区で行われた水田工事の際に出現した立木の写真を目にしたことから始まった。
1983年にほ場整備工事が行われた時、地表下1〜2m(*1)に直立する立木の頭が現れた。工事業者が立木を撤去するために周囲を掘り下げたところ、5m前後まで掘っても幹がまだ続いていた。松井氏は、その時に撮影された写真を目にして、三瓶火山の活動と関係して形成された大規模な埋没林が存在することを予測、独自に調査を行った。ボーリング調査等の結果から、小豆原の谷が火山灰に埋もれており、その下に古土壌と見られる有機質の泥層が存在することが分かり、10mを超える幹を有する埋没林が存在する可能性が高くなった。松井氏の調査結果を受け、島根県が三瓶自然館の拡充整備事業の一環として発掘調査を行ったところ、1998年秋に複数の立木を確認、年代測定の結果、縄文時代後期に埋没したものと判明した。これにより、世界でも例を見ない(*2)規模の三瓶小豆原埋没林が発見された。
三瓶火山の活動に関係する埋没林は、小豆原地区以外にも存在する。同時期のものでは、神戸川下流の三田谷I遺跡(出雲市)で広葉樹を中心とする埋没林が確認されている。大田市川合町の静間川河床、大田市大田町の三瓶川河床にも数本の立木が存在し、周辺の地下に埋没林が存在するとみられる。三瓶山麓には断片的に存在する埋没立木もいくつかある。倒木として埋もれているものは数多く、工事や洪水による浸食によって出現した例が多くある。古い活動期のものでは、約5万年前の第2活動期で埋没した横見埋没林(出雲市佐田町)がある。

図3-3 松井整司氏が独自の調査結果に基づいて、埋没林発見時に作成した埋没状況のイメージ図
*1 地表下1〜2m:三瓶小豆原埋没林の立木の頂部は、地表下1〜2mの高さにあり、これは地下水面の高さを反映している。地下水面より深い部分は朽ちずに残り、地下水面より高い部分は朽ちて失われ、どの立木もほぼ同じ深さに頂部がある。
*2 世界でも例を見ない:三瓶小豆原埋没林のように幹を残した埋没林は極めて例が少なく、これほど大きな規模のものは世界的にも報告例がない。
4)縄文時代の気候と植生変化
縄文時代は、最終氷期(*1)の最寒冷期(2万〜1万6000年前)から温暖期に向かう時期に始まり、気候最適期と呼ばれる7000〜6000年前の温暖期を経て、水稲稲作が日本に広く伝播した2500年前頃まで続く時代区分である。約1万年間に及ぶ時代で、その間に気候の変化に伴って植生や海岸地形が大きく変化してきた。
島根県では、花粉分析(*2)により縄文時代から現代に至る植生変化の歴史の解明が進んでいる。特に、宍道湖の湖底には過去1万数千年間溜まり続けている泥の地層があり、そこには水や風によって周辺から運ばれた花粉が含まれており、その組成から植生変化が連続的に追跡できる。これによると、9000年前頃から7500年前頃にかけての時期には、冷温帯の気候に多いブナやツガが多く、現在の中国地方では標高1000m前後の高地に分布する樹木が優先していた。その森は7500年前頃を境にカシ・シイを主体とする暖温帯型の照葉樹林に代わっていった。照葉樹林帯に分布する落葉広葉樹のナラ類も同時期に多く、その傾向は500年前頃まで継続する。三瓶小豆原埋没林のスギ林が生育していた4000年前頃は、暖温帯型の植生が分布していたと推定できる。
宍道湖の花粉分析では、最終氷期以降の全段階を通じて、スギの出現が少ない。しかし、石見地方の堆積物ではスギが縄文時代に圧倒的に多く分布することがあり、成育に適した環境にはスギ林が存在していたと推定される。

図3-4 宍道湖湖心SB1コアの花粉分析結果
(大西郁夫・干場英樹・中谷紀子(1990)宍道湖湖底下完新統の花粉群.島根大学地質学研究報告,9,117-127.より引用、加筆)
*1 最終氷期:約10万年前に始まり、。1万1000年前に終了した氷期。最寒冷期には、中緯度地方の平均気温は現在より5℃程度低かったと推定されている。
*2 花粉分析:花粉は丈夫な殻を持ち、泥質の堆積物中にしばしば含まれている。その花粉の量比から植生復元を行ったり、過去の気候解析にも有用である。
4.埋没林形成の謎
1)埋没林を埋めた地層
三瓶小豆原埋没林では、最大約13mの幹が残る立木が直立状態で埋もれている。「埋没林」として知られているもので、これほど長い幹が残存するものは他に例がなく、魚津埋没林をはじめ多くのものは根株部分が残るのみである。三瓶小豆原埋没林の形成には、なんらかの特殊な事情があったことがうかがわれる。
三瓶小豆原埋没林を埋めている地層は、三瓶火山の噴出物からなる。その地層は、縄文時代の小豆原の谷を埋めて堆積していて、堆積様式から大きく3層に区分できる。その地層は、上から順に、“水流で運ばれて水底に堆積した火山灰層(火山灰の二次堆積層)”、“火砕流(*1)堆積層”、“土石流(*2)堆積層”である。
一般的に、火砕流や土石流は強大なエネルギーを持った土砂の流れで、火砕流は樹木を炭化させるほどに高温の場合もある。これらの流れに直撃されると、多数の樹木が立ったままで残ることは普通は考えにくい。三瓶小豆原埋没林を埋めた土石流の地層には、幹径1〜2mの流木や、土石流に運ばれた直径3mを超える土塊も含まれていて、そのエネルギーが強大であったことを物語っている。火砕流堆積層は、その中に含まれる木片には炭化したものが多く、立木の樹皮表面の火砕流に覆われた部分は炭化している。堆積時の温度は300℃前後と推定されており、樹木を炭化させるには十分の温度があったにも関わらず、立木の炭化は樹皮表層のみで、材には全く及んでいない。すなわち、三瓶小豆原埋没林は、押し倒されたり、炭化しても不思議ではない条件にさらされながら、立ったままで残ったことになる。
また、谷は浸食作用が卓越する場である。火山噴火や斜面崩壊によって短期的に堆積した未固結の土砂は浸食して失われるのも早い。小豆原の谷では、堆積物があまり浸食されずに残っている。このことも幹が残ったことと関わりがある。

図4-1 小豆原埋没林の地質断面図
*1 火砕流:火山灰や軽石、火山礫などの火砕物が火山ガスと一体となって流下する現象。高温のものは500℃を超えることもある。
*2 土石流:多量の水を含んだ土砂が斜面を流下する現象。
2)土石流の流下経路
三瓶小豆原埋没林を埋めた地層の最下位にある土石流堆積層は、谷の下流側で厚く、上流側で薄くなる。その中には多量の流木が含まれ、それは立木に対して下流側に絡みつく産状を示す。これらのことは、土石流が谷の下流側から流入したことを物語る。
この土石流に対応するとみられる地層は、小豆原の南隣の谷筋(伊佐利川)に厚く分布している。三瓶山北の原付近まで土石流堆積層が連続していて、規模が大きな山体崩壊に伴って発生したものと推定される。伊佐利川の谷は三瓶火山の火山体のすそ部を谷頭としている。一方、小豆原川は山麓の丘陵地に端を発しており、三瓶火山から流下する土砂の直接の経路にはならない。小豆原川と伊佐利川は、埋没林の下流約700m地点で合流していて、合流部にも土石流の堆積物が厚く分布している。これらのことから、埋没林を埋めた土石流は、三瓶火山の山体崩壊(*1)で発生し、伊佐利川の谷を流れ、一部が小豆原川の合流部から逆流して埋没林の地点まで達したと推定される。土石流の末端部に流木が集中することはしばしば観察される現象である。埋没林地点は谷を逆流した土石流が停止した末端部分で、この地点の立木は倒れずに根元部分が土石流によって埋没したと考えられる。
埋没林の地点のすぐ下流側では、尾根の鞍部を乗り越えて伊佐利川の谷から小豆原の谷に流下した土石流堆積物が堆積錐地形を作っており、この地形が逆流して浸入した土石流の勢いを弱める働きをした可能性もある。
小豆原の谷は、合流部を土石流によって埋められたことで、土砂ダム(せき止湖)の状態になった。これにより、土砂が厚く堆積し得る空間が生まれ、そこを埋めた堆積物(*2)によって幹が深く埋もれることになった。

図4-2 埋没林を埋めた土石流と土砂ダムのイメージ図
*1 山体崩壊:北の原一帯には、山体崩壊の土砂が堆積してできた起伏がみられ、その堆積物は巨大な土砂ブロックを含んでいることから、4000年前の火山活動時に規模が大きい山体崩壊が発生したと推定できる。その跡地形は残っておらず、その後の噴出物で隠された可能性が高い。
*2 そこを埋めた堆積物:土砂ダムの状態になったことで、火山灰の二次堆積層が厚く堆積することができた。この地層がなければ、埋没林の規模は範囲、残存する幹の規模ともかなり小規模なものに留まっていた。
3)火砕流の堆積
土石流堆積層の直上には、火砕流堆積層が重なる。この地層は火山灰を中心とする比較的細粒な火砕流(火山灰流)の堆積物で、層厚は最大3m以上に達する。この地層に含まれる木片は炭化していて、小豆原に達した時点で300℃前後の温度があったと推定されている。
火砕流はガス体として流下(*1)する。供給源の火口から火砕流が直進してきた場合、小豆原の谷は火砕流の進行方向に直交している。谷底に生えている樹木は、南側の尾根が「防風壁」の役割を果たすことで、火砕流の破壊力をある程度免れた可能性が高い。高速の火砕流を受けた樹木に火山礫が食い込む事例があるが、小豆原の立木にはそのような状態は見受けられなかった。
小豆原に堆積した火砕流は、材を炭化させる温度を持っていた。これが厚さ3mで堆積した場合、通常は内部の温度が低下するまでにはある程度の時間を要するため、火砕流に覆われた部分の材は炭化が進行し得る。ところが、埋没林の立木は、樹皮表層は炭化しているものの内部は炭化していない。このことは、流下した瞬間は高温だったが、堆積直後に温度低下したことを示唆する。
火砕流の温度を低下させた理由として考えられる要素に、水の存在がある。火砕流の流下時点では、小豆原の谷は土砂ダムの状態になっていて、ある程度の量の水が存在した可能性がある。湖沼状の水がなくても、小豆原川があることで水は瞬時に供給される。この水が火砕流の温度を急速に低下させたことが考えられる。この仮説の根拠となるものとして、火砕流堆積層にみられた二次噴気孔がある。高温の火砕流堆積物に水分を含んだ材など、ガスの発生源となる物質が含まれた場合、それから発生したガスが堆積物中を通過して抜けた痕跡を二次噴気孔と呼ぶ。細粒な粒子がガスとともに放出されることで、ガスの通り道は周囲よりも粗粒な粒子の割合が高くなる。埋没林を埋めた火砕流堆積層の下部には、二次噴気孔が著しく発達した個所が認められた。特にガス発生源となるような材はなかったことから、堆積時に存在した水が蒸発したと考えられる。また、火砕流堆積層の上面が、上位に重なる水成の二次堆積層に連続的に変化する様子も観察され、これらの水が温度低下に影響した可能性があると推定される。

図4-3 火砕流中の二次噴気孔のイメージ図
*1 ガス体として流下:火砕流は、火砕物とガスが混じりあった状態で、高密度のガス体としての動きをする。
4)地下水中での保存
三瓶小豆原埋没林の出土樹木は、外見的にはほとんど劣化しておらず、強度は落ちているものの、スギについては工芸等の材料として使える状態である。約4000年の時間を経て、良好に保存された要因は、地下水中に閉じこめられて空気に触れなかったことである。
埋没林を埋めた地層は、谷を埋めたものであるため、多量の地下水を含んでいる。発掘当時は、地表から1m程度の深さで水が湧き出す状態だった。地下水には酸素がほとんど含まれておらず、材を分解する微生物の大部分は地下水中では生息できない。そのため、材の劣化(*1)は極めてゆっくりとしか進行せず、生育時とほとんど変わらない形状を留めることができた。缶詰めや真空パックと同じ状態である。なお、埋もれた樹木の地表に露出していた部分や、空気の影響を受ける地下浅い部分は腐朽して失われた。
樹木を深く埋めた地層が維持され、地下水位が高い条件が維持されたことは、三瓶小豆原埋没林の特殊性のひとつである。谷を埋めた堆積物は浸食速度も速く、通常なら小豆原の堆積物も大部分が浸食され、あるいは谷の深さがもとの谷底高度まで下ることで地下水位が低下し、直立状態の長い幹が残ることは難しい。小豆原の堆積物は浸食を免れた。
浸食を免れた理由は、堆積した土砂状を流れ始めた河川が、硬い基盤岩の高まり部分で固定され、もとの谷底高度まで浸食が進まなかったことによる。小豆原川と伊佐利川の合流点から下流約300mに「稚児滝」がある。この滝の岩盤が、“硬い基盤岩の高まり”にあたる。現在、稚児滝より下流では深い谷地形であるが、これより上流は土石流堆積物が作る堆積地形が広がっている。両者の高度差は20〜40mにも達する。稚児滝の南方約50mの地点で実施されたボーリングでは、地表から40m下に埋没林形成以前の谷底が確認されていて、河川が稚児滝部分で固定されなければ、その深度まで浸食が進み、小豆原の堆積物の流失していた可能性が高い。基盤岩の高まりがあり、その部分で河川が固定されるという偶然の重なりが、三瓶小豆原埋没林の巨大な幹を残した大きな要因である。火山噴火による谷の埋積、土砂ダムの形成は、数千年、数万年の時間単位では珍しい現象ではなく、過去に三瓶小豆原埋没林と同様に長い幹を残したまま埋もれた森も多数あったと思われる。しかし、同様の埋没林が他に知られていないことは、稚児滝によって土砂の流出が免れたことが、縄文の森をそのままの姿で残した要因として大きいことを示すと言えるだろう。

図4-4 合流点での河道固定のイメージ図
*1 材の劣化:無酸素の地下水中に生息する嫌気性の微生物もあり、また材の成分が直接溶出することもあるため、材の劣化はゆっくりと進行する。仮に、そのまま数十万年経過すると、多くの場合、材は劣化して土圧に押しつぶされるようになる。